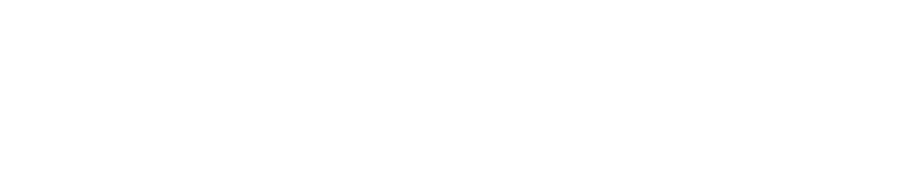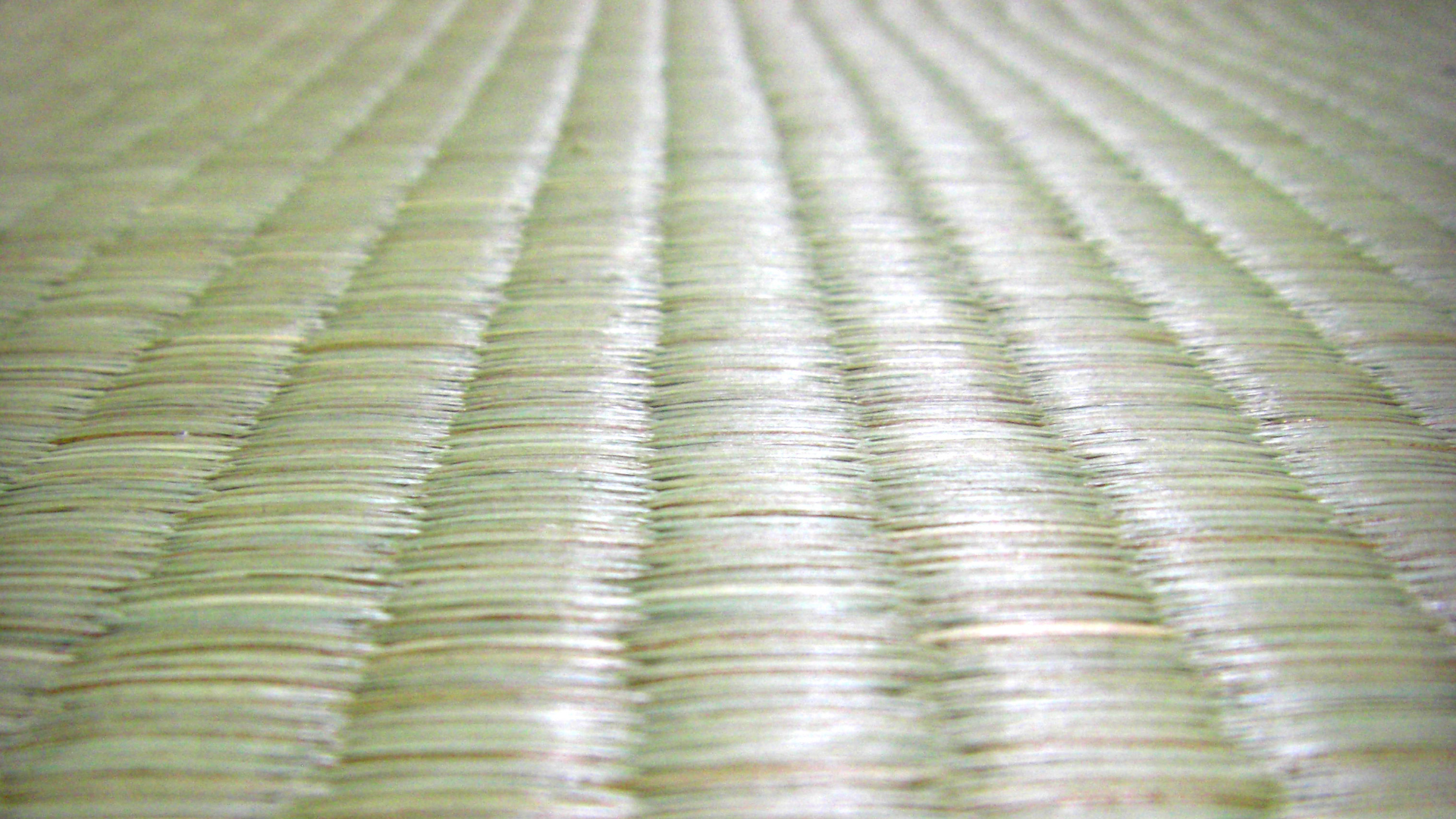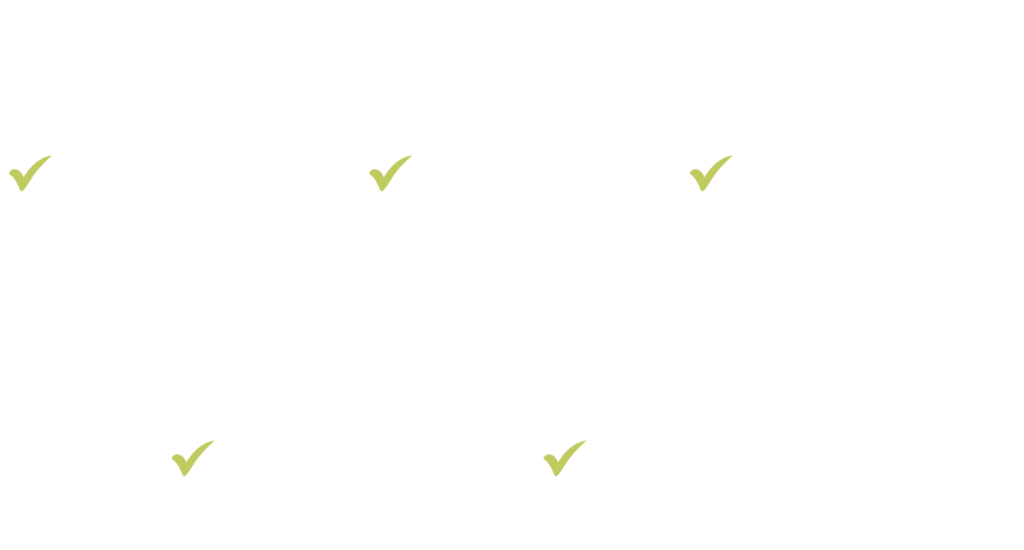畳の構造
畳は、「畳床」「畳表」「畳縁」という3つの要素から成る、シンプルな構造を持つ伝統的な床材です。
「畳床」は、重ねた稲藁を圧縮して固めた基盤で、その上に天然い草を経糸に織り込んだ「畳表」を被せ、さらに長辺に「畳縁」を縫い付けて仕上げられます。
現在では、住宅事情やニーズの変化、科学技術の進化により、多様な素材が用いられるようになりましたが、畳の基本的な構造や製法は、昔からほとんど変わっていません。
ここでは、「畳床」「畳表」「畳縁」のそれぞれについて、その特徴を詳しくご紹介します。
畳 床(たたみどこ)
畳床は、かつては稲藁を何層にも重ねた天然素材100%の「藁床」が一般的でした。しかし、近年では住宅事情の変化や稲藁の生産量の減少に伴い、藁床に代わり、木材チップを圧縮した下地材にスタイロフォーム(断熱材)を挟み込んだ軽量な建材畳床が主流となっています。
畳 表(たたみおもて)
畳表は、経糸にい草を織り込んで作られ、その質や長さ、色合い、本数によって等級が決まります。
上質な畳表は、選び抜かれた良質ない草を使用し、丈夫な経糸にしっかりと織り込まれているため、耐久性に優れています。また、長いい草を使用しているため、畳の端に色むらが生じることがなく、美しい色合いと鮮やかさが特徴です。
畳 縁(たたみべり)
畳縁は、かつては綿糸が主に使われていましたが、近年では化学繊維製のものが主流となっています。化学繊維製の畳縁はコストが抑えられ、耐久性にも優れていますが、質感においては綿糸の方が勝っているといえるでしょう。
また、無地のものや柄入りのものが選べます。さらに、寺院や床の間で用いられる特別な「紋縁」も存在し、格式のある場にふさわしい装飾として用いられています。
畳の良さ
畳は、ただの床材以上の存在です。日本の伝統的な生活文化の中で重要な役割を果たし、独自の魅力を持っています。柔らかな感触や優れた湿度調整機能、さらにはリラックス効果をもたらす香りなど、畳ならではの良さは日々の暮らしに多くの恩恵をもたらします。畳の魅力を理解し、活用することで、より快適で健康的な生活空間を作り上げることができます。
湿度調整
い草畳は優れた湿度調整機能を備えており、室内の湿度を適切に保つ働きがあります。湿度が高いときには湿気を吸収し、乾燥しているときには蓄えた水分を放出することで、室内の湿度を自然に調節します。この調湿効果は、湿気の多い日本の気候において快適な室内環境を維持するのに大いに役立ちます。
消臭効果
い草畳には、空気中のさまざまなニオイや有害物質を浄化する力があり、室内の空気を清潔に保つ効果があります。たとえば、二酸化窒素やVOC(揮発性有機化合物)といった人体に悪影響を及ぼす物質を吸着し、空気をきれいにしてくれます。
リラックス効果
い草の香りにはリラックス効果があるとされており、い草の主成分であるフィトンチッドや芳香成分には、心身をリラックスさせる効果があることが科学的にも示されています。これらの成分は森林浴で感じる香りに似た作用を持ち、心拍数を落ち着かせたり、自律神経を整える働きが期待できます。畳の香りが作り出す穏やかな空間は、家族の団らんや、ひとり時間をより快適で心地よいものにしてくれるでしょう。
断熱効果
空気には熱を伝えにくい性質があり、畳はその特性を活かした優れた構造を持っています。畳表に使用されているい草はもちろん、畳床に使われるワラも内部がスポンジ状になっており、多くの空気を含むことで断熱性と保温性を高めています。
弾力効果
畳表に使用されているい草は、スポンジ状の構造を持ち、適度な弾力性があります。この弾力性により、万が一お年寄りや小さなお子様が転んでも、衝撃を和らげてくれるため、安心して過ごすことができます。い草の柔らかさと弾力は、特に家庭内での安全性を高める要素として、畳の大きな魅力の一つと言えるでしょう。
吸音効果
畳の部屋はフローリングの部屋に比べて静けさを感じやすいです。これは、畳が多くの空気を含んでおり、その構造が音や衝撃を吸収するためです。畳が持つ柔らかく弾力のある性質が、足音や物が落ちたときの音を和らげ、室内の騒音を減少させて静かな空間を作り出します。これにより、家の中でより落ち着いた雰囲気を楽しむことができるのです。
畳のお手入れ
畳は長年の使用にも耐え、私たちの生活に多くの利点をもたらしてくれます。畳をより長く快適に使い続けるためには、定期的なお手入れが欠かせません。畳の表面や畳床をしっかりとケアすることで、快適な生活空間を維持し、畳の美しさと機能を最大限に引き出すことができます。ここでは、畳のお手入れ方法についてご紹介します。
定期的なメンテナンスで長持ち!
裏返し: 新畳を使用してから約3〜5年後には裏返しを行い、青味の残った畳にすることで、長持ちさせることができます。裏返しは畳表の擦れ具合や焼け具合によって、適切なタイミングで行いましょう。
表替え: 約5〜10年ごとに畳表が傷んできたら、表替えを行いましょう。畳表がささくれたり、擦り切れたり、縁が切れた場合は表替えをお勧めします。
畳床と床板の点検
定期的に畳床と床板の乾燥状態をチェックしましょう。また、白アリなどの害虫が発生していないかを早期に確認することも大切です。
お手入れ方法
拭き掃除: 乾いたタオルで拭くことをおすすめします。新畳の場合、水拭きは避け、カラ拭きが基本です。もし水拭きが必要な場合は、タオルを軽く濡らして脱水機で余分な水分を取ってから使用してください。
掃除機の使用: 畳の目に沿って、静かに何度か往復して掃除機をかけてください。掃除後は、軽く拭き掃除をするとより清潔になります。
注意点
畳の上にジュータンや薄緑(ゴザ)は敷かないようにしましょう。畳の下に新聞紙を敷かないことが大切です。一階は湿気がたまりやすいため、新聞紙を敷くのは避けましょう。防虫・防湿紙を使用するのが最適です。当店でも防虫・防湿紙を取り扱っておりますので、必要な場合はお求めください。
畳のサイズ
畳のサイズは、地域や用途によって異なるため、選ぶ際にはその特徴を理解することが大切です。日本各地で使われる畳のサイズには、伝統的な京間や江戸間、そして現代の団地サイズなど、さまざまな種類があります。それぞれのサイズには歴史的背景や地域性が反映されており、選ぶ場所や目的に応じて最適なサイズを選ぶことで、より快適な空間を作り上げることができます。
| 畳の種類 | サイズ (長さ x 幅) | 主な地域 |
|---|---|---|
| 京間(本間) | 6尺3寸 × 3尺1寸5分 (191 cm x 95.5 cm) | 京都を中心に関西地方 |
| 中京間 | 6尺 × 3尺 (182 cm x 91 cm) | 名古屋を中心に中京地方 |
| 江戸間 | 5尺8寸 × 2尺9寸 (176 cm x 88 cm) | 東京を中心に関東地方 |
| 団地サイズ | 5尺6寸 × 2尺8寸 (170 cm x 85 cm) | 団地等 |